11月下旬になって、ようやく寒さが本格的になってきました。
原木しいたけ栽培セットBCEXをお買い上げいただきましたお客様、そのBCEXの品種でも本格的な打撲浸水前の走り子が出始める季節となりました。
一方で、今の時期、北風が吹くなどして、寒すぎて、あるいは乾き過ぎて、しいたけが成長できない場合があります。
この時期のしいたけは、肉が締まって大変美味しい季節です。
せっかく生えてきたしいたけが、より大きくより肉厚に、そして、美味しく育つよう、お願いがあります。

見にくくて申し訳ないのですが、上の写真は、しいたけに袋をかけたものです。
この様にすると、①風よけ、②寒さ除け、③雨が降っても雨子にならない、などの良いことがあります。
袋は、ホームセンターなどで売っている10号のFGポリ袋がちょうどよい大きさです。
風で飛ばされないように、袋を輪ゴムなどで留めてください。

椎茸に袋をかける時期ですが、上の写真くらいの大きさ(3cm)くらいになったら、袋をかけてください。
椎茸が美味しく育ちますように。


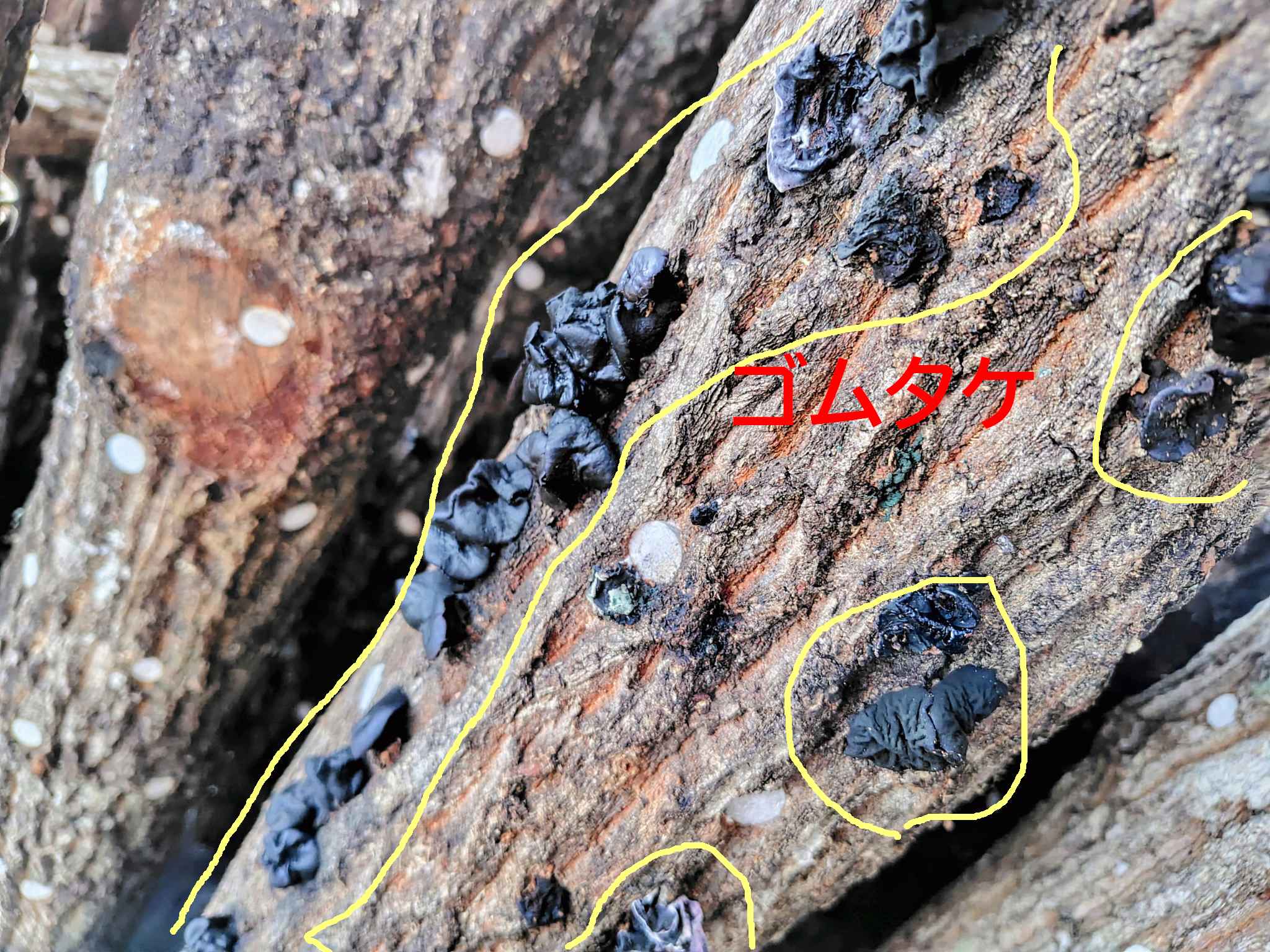
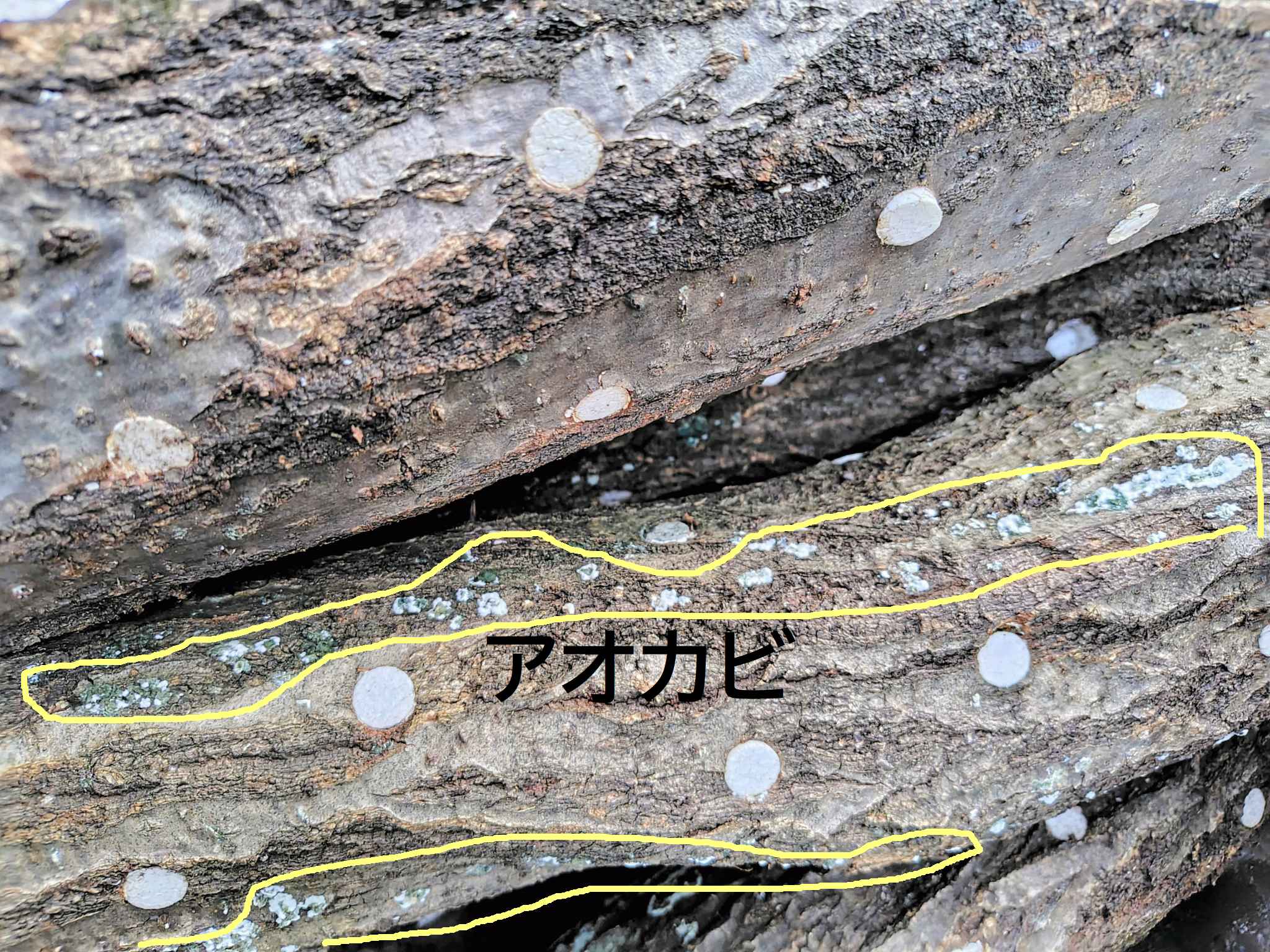



.jpg)
